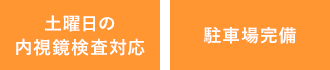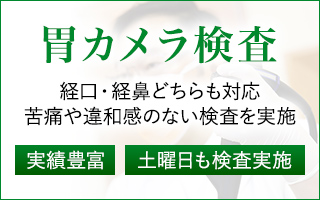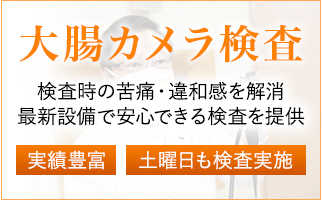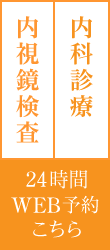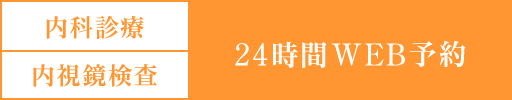【新常識】健康診断で肝臓の数値が…それ、放置は危険!「脂肪肝」の最新知識「MASLD」を徹底解説…さらに新分類「MetALD」
「健康診断の結果を見て、肝臓の数値にドキッとした…」
「最近なんだか疲れやすい。お酒はそんなに飲まないのに、なぜ?」
そんな経験はありませんか?
もしかしたら、それは「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓からの静かなSOSかもしれません。その正体は、日本人の3〜4人に1人が抱えているとも言われる「脂肪肝」です。
「脂肪肝って、太っている人やお酒好きの人の病気でしょ?」——そう思っているなら、ぜひこの記事を読み進めてください。実は、その常識はもう古いかもしれません。
2023年、脂肪肝の呼び方や定義が世界的に大きく見直され、「MASLD(マスルド)」という新しい考え方が標準となりました。 これは、痩せている人やお酒をあまり飲まない人にも無関係ではない、非常に重要な変化です。
この記事では、最新の研究に基づき、以下の点をどこよりも分かりやすく解説していきます。
そもそも「脂肪肝」ってどんな状態?
なぜ「NAFLD」から「MASLD」に名前が変わったの?
新しい常識「MASLD」とは?あなたも当てはまるかチェック!
放置するとどうなる?脂肪肝の恐ろしい末路
今日からできる!脂肪肝の改善・予防策
(※本記事は、論文「脂肪性肝疾患(Steatotic liver disease: SLD) のパラダイムシフト: NAFLD から MASLDへ」の内容を参考に、専門的な情報を分かりやすく解説したものです。)
そもそも「脂肪肝」ってどんな病気?
脂肪肝とは、その名の通り「肝臓に脂肪(主に中性脂肪)が過剰に蓄積した状態」です。
美味しい高級食材「フォアグラ」を想像してみてください。あれは、ガチョウやアヒルにたくさんエサを与えて、肝臓を人工的に脂肪肝にしたものです。人間の肝臓でも、食べ過ぎや飲み過ぎによって同じような状態が引き起こされます。
通常、肝臓に含まれる脂肪の割合は5%程度ですが、脂肪肝では30%以上が脂肪で占められてしまうこともあります。
初期の脂肪肝には、ほとんど自覚症状がありません。これが「沈黙の臓器」と呼ばれる所以です。しかし、静かに、そして確実に肝臓を蝕んでいく、決して侮れない病気なのです。
なぜ名前が変わったの?「NAFLD」から「MASLD」へのパラダイムシフト
これまで脂肪肝は、大きく2つに分けられていました。
アルコール性脂肪性肝疾患(AFLD): 明らかに飲み過ぎが原因のもの。
非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD:ナッフルディー): アルコール以外の原因(肥満、糖尿病、脂質異常症など)によるもの。
しかし、この「NAFLD」という呼び方には、いくつかの問題点が指摘されていました。
問題点①:「非アルコール」では原因が分からない
「アルコールが原因ではない」という否定的な定義では、病気の根本的な原因である「代謝機能の異常(メタボリックシンドローム)」が伝わりにくい。
問題点②:飲酒量の線引きが曖昧
「じゃあ、どれくらい飲むとアルコール性になるの?」という基準が曖昧で、少〜中等量の飲酒をする人が分類しづらい。
問題点③:「Fatty(脂肪の)」という言葉への配慮
「Fatty」や「Alcoholic」といった言葉が、肥満やアルコール依存症に対する差別的な印象(スティグマ)を与えかねない。
これらの課題を解決し、より病態を正確に反映するために、世界中の専門家たちが議論を重ね、2023年に新しい疾患名「MASLD(Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease)」が提唱されたのです。
日本語では「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患」と呼ばれます。 77この変更は、日本肝臓学会を含む世界の70以上の組織に支持されており、国際的なコンセンサスとなっています。
新しい世界の常識!「MASLD」とは?
MASLDの最大の特徴は、「〜ではない」という消去法的な診断(除外診断)ではなく、
「代謝機能の異常があること」を積極的に診断の根拠とする(組み入れ基準)点です。
具体的には、まず画像検査や血液検査などで「脂肪肝(Steatotic Liver Disease: SLD)」があることを前提とします。その上で、
以下の5つの心代謝系危険因子のうち、1つでも当てはまれば「MASLD」と診断されます。
【MASLD診断チェックリスト】
あなたの脂肪肝は、MASLDかもしれません。以下の5項目のうち、1つ以上当てはまりますか?
肥満
BMIが23以上(アジア人の場合)
または、腹囲が男性94cm以上、女性80cm以上
血糖値の異常
空腹時血糖値 ≧ 100 mg/dL
または、HbA1c ≧ 5.7%
または、2型糖尿病と診断されている・治療中である
血圧の異常
血圧 ≧ 130/85 mmHg
または、降圧薬(血圧を下げる薬)を服用中である
脂質の異常(中性脂肪)
血清中性脂肪値 ≧ 150 mg/dL
または、脂質異常症の治療中である
脂質の異常(HDLコレステロール)
血清HDL(善玉)コレステロール値が男性 ≦ 40 mg/dL、女性 ≦ 50 mg/dL
または、脂質異常症の治療中である
いかがでしたか? BMIが標準でも、血圧が少し高いだけでMASLDに該当する可能性があります。これまで「痩せているから大丈夫」と思っていた人も、他人事ではないのです。
【新設】お酒を飲む人のための新分類「MetALD(メット・エーエルディー)」
「MASLDの基準にも当てはまるけど、お酒も結構飲むんだよな…」という方向けに、新しいカテゴリーが作られました。それが「MetALD(Metabolic dysfunction-associated and increased alcohol intake)」です。
これは、MASLDの基準を満たし、かつ中等量以上の飲酒(男性:週210g〜420g、女性:週140g〜350g)がある場合に分類されます。 12 週210gのアルコールとは、ビールなら1日あたりロング缶1本(500ml)、日本酒なら1日1合程度に相当します。
代謝異常とアルコールの両方が肝臓にダメージを与えるため、特に注意が必要なグループと言えます。
「たかが脂肪肝」と放置は絶対ダメ!忍び寄る”肝臓病の三段跳び”
MASLDの本当に怖いところは、自覚症状がないまま静かに進行し、命に関わる病気へと進展していく可能性がある点です。この進行は、「脂肪肝 → 肝炎 → 肝硬変 → 肝がん」という”肝臓病の三段跳び”とも言えるプロセスを辿ります。
ステップ1:MASLD(単純性脂肪肝)
肝臓に脂肪が溜まっているだけの状態。この段階なら、生活習慣の改善で十分に正常な肝臓に戻れる可能性があります。
ステップ2:MASH(マッシュ:代謝機能障害関連脂肪肝炎)
溜まった脂肪が引き金となり、肝臓に炎症が起きて肝細胞が壊れ始めた状態です。以前は「NASH(ナッシュ)」と呼ばれていました。 放置すると、肝臓は徐々に硬くなっていきます。
ステップ3:肝硬変
炎症が長く続いた結果、肝臓が硬くゴツゴツになり、本来の機能を果たせなくなった状態。一度肝硬変になると、元の健康な肝臓に戻ることは極めて困難です。
ステップ4:肝がん
肝硬変の状態から、高い確率で肝がんが発生します。近年の日本では、ウイルス性肝炎が原因の肝がんは減少し、MASLDのような非ウイルス性の原因による肝がんが増加しています。
健康診断で「脂肪肝」や「肝機能異常」を指摘されたら、それはこの恐ろしいプロセスの入口に立っているというサインなのです。
どうすれば改善できる?今日から始めるMASLD対策プロジェクト
「もう手遅れかも…」と不安になった方も、ご安心ください。MASLD(特にMASHに進む前)は、生活習慣の見直しによって改善が期待できる病気です。特効薬に頼る前に、まずは食事と運動という2つの柱を立て直しましょう。
1.食事療法:何を減らし、何を摂るか
基本は「適切なカロリー摂取」と「栄養バランス」です。
減らすべきもの
糖質の多いもの:ご飯・パン・麺類の大盛り、甘い菓子パン、ジュース、果物の食べ過ぎ。特に果物に含まれる「果糖」は中性脂肪に変わりやすいので要注意。
脂質の多いもの:揚げ物、炒め物、脂身の多い肉、バターや生クリームをたっぷり使った洋菓子。
アルコール:MetALDやアルコール性肝障害のリスクがある方は、禁酒・節酒が必須です。
積極的に摂りたいもの
良質なタンパク質:脂肪の少ない赤身肉、鶏むね肉、魚、大豆製品(豆腐・納豆など)。肝臓の再生を助けます。
食物繊維:野菜、きのこ、海藻類。血糖値の急上昇を抑え、脂質の吸収を穏やかにします。
ビタミン・ミネラル:緑黄色野菜など。肝臓の働きをサポートします。
いきなり全てを変えるのは大変です。「夕食のご飯を半分にする」「お菓子をナッツに変える」「野菜スープを1品加える」など、できることから始めましょう。
2.運動療法:脂肪を燃やす習慣を
食事療法とセットで行うことで、効果は倍増します。
有酸素運動:内臓脂肪を燃焼させるのに効果的です。
例:ウォーキング、軽いジョギング、サイクリング、水泳など。
目安:「少しきつい」と感じるくらいの強度で、1回30分以上、週に3〜5日。
筋力トレーニング:基礎代謝を上げて、太りにくく痩せやすい体を作ります。
例:スクワット、腕立て伏せ、腹筋など。
大きな筋肉(太もも、背中、胸)を鍛えるのが効率的です。
運動も「エレベーターを階段にする」「一駅手前で降りて歩く」といった”ながら運動”から始めるのが長続きのコツです。
3.薬物療法:最終手段としての選択肢
食事や運動で改善しない進行したMASHの場合、医師の判断で薬物療法が検討されることがあります。2024年には、米国でMASH治療薬として「レスメチロム」が初めて承認されるなど、治療の選択肢も少しずつ増えています。 14141414 ただし、あくまで基本は生活習慣の改善であることを忘れないでください。
まとめ:沈黙の臓器からのSOSを見逃さないで
脂肪肝の常識は、「NAFLD」から「MASLD」へと大きく変わりました。これは単なる名前の変更ではなく、「脂肪肝は代謝機能の異常という、全身に関わる問題のサインである」という重要なメッセージが込められています。
脂肪肝の新常識は「MASLD」。代謝異常が1つでもあれば該当する。
痩せていても、お酒をあまり飲まなくても、誰でもなる可能性がある。
放置すれば、肝炎・肝硬変・肝がんへと進行する恐れがある。
改善の鍵は「食事」と「運動」。生活習慣の見直しで、肝臓は健康を取り戻せる。
健康診断の結果は、あなたの体からの大切なお便りです。もし「肝機能」の項目にチェックがついていたら、それは「生活を見直す絶好のチャンス」と前向きに捉えましょう。
この記事が、あなたの肝臓の健康を守るための一歩となれば幸いです。気になる症状や検診結果があれば、決して自己判断せず、かかりつけ医や消化器内科の専門医に相談してくださいね。