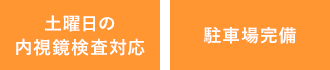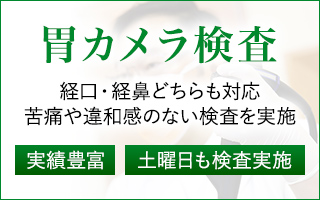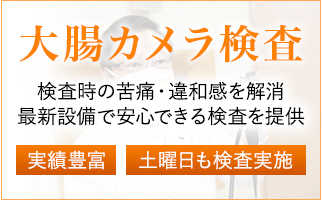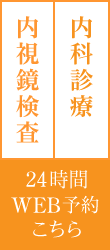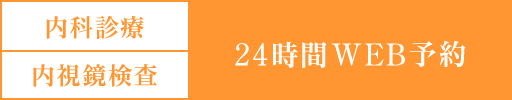便潜血検査とは
 便潜血検査は、便を採取して眼に見えない微量の血液が便に含まれていないかを調べる検査です。一般的な健康診断で実施される検査でもあります。主に、大腸がんのスクリーニング検査として実施しています。便潜血検査で陽性と指摘されたら、大腸カメラ検査を受けることをお勧めしております。便潜血検査陽性で大腸カメラ検査を受けた場合、約30~40%が大腸ポリープ、約3~4%が大腸がんを発見されます。また、前がん病変である大腸ポリープが発見された場合は、その場でポリープの切除処置を行っております。ただし、便潜血検査で陰性であった場合でも、早期大腸がんや大腸ポリープなどを見逃していることがあります。
便潜血検査は、便を採取して眼に見えない微量の血液が便に含まれていないかを調べる検査です。一般的な健康診断で実施される検査でもあります。主に、大腸がんのスクリーニング検査として実施しています。便潜血検査で陽性と指摘されたら、大腸カメラ検査を受けることをお勧めしております。便潜血検査陽性で大腸カメラ検査を受けた場合、約30~40%が大腸ポリープ、約3~4%が大腸がんを発見されます。また、前がん病変である大腸ポリープが発見された場合は、その場でポリープの切除処置を行っております。ただし、便潜血検査で陰性であった場合でも、早期大腸がんや大腸ポリープなどを見逃していることがあります。
便潜血検査で陽性と指摘されたら
便潜血検査陽性と指摘された場合、食道・胃・十二指腸・大腸・小腸・肛門のいずれかの部位で出血があります。便潜血検査陽性の段階で発見される大腸がんは、早期治療が可能なため、比較的楽に完治できる場合がほとんどです。そのため、便潜血検査陽性と指摘された場合は、速やかに大腸カメラ検査を受けることをお勧めしております。このように、便潜血検査陽性は、大腸カメラ検査を受ける良い機会と受け止めて、なるべく早めに当院までご相談ください。
苦痛のない大腸カメラ検査
 当院では、患者様の苦痛のない大腸カメラ検査を実施しております。最新の内視鏡システムを導入、高い技術と豊富な経験を有する専門医師によって、質の高い検査を受けることができます。軽い鎮静剤を用いた無痛検査も可能です。 なお、大腸カメラ検査中に大腸ポリープや早期大腸がんなどの異常を発見した場合は、その場で切除治療を行います。この場合、日帰り手術が可能なため、入院の必要なく当日そのままご帰宅頂けます。 短時間で患者様の負担が少ない大腸カメラ検査を行っておりますので、大腸カメラ検査が苦手な方もどうぞ安心して当院までご相談ください。
当院では、患者様の苦痛のない大腸カメラ検査を実施しております。最新の内視鏡システムを導入、高い技術と豊富な経験を有する専門医師によって、質の高い検査を受けることができます。軽い鎮静剤を用いた無痛検査も可能です。 なお、大腸カメラ検査中に大腸ポリープや早期大腸がんなどの異常を発見した場合は、その場で切除治療を行います。この場合、日帰り手術が可能なため、入院の必要なく当日そのままご帰宅頂けます。 短時間で患者様の負担が少ない大腸カメラ検査を行っておりますので、大腸カメラ検査が苦手な方もどうぞ安心して当院までご相談ください。
便潜血検査陰性の方へ
便潜血検査で陰性だった場合、病変があっても便が柔らかかったり、便が通過する部位に隆起のない病原があったりと、便が擦れても出血しないことがあります。この場合、便潜血検査では出血が見られないまま病状が進行することがあります。また、大腸ポリープの大半と、早期大腸がんの約半分、進行大腸がんの約1割が便潜血検査陰性となるとの調査結果もあります。このため、便潜血検査で結果が陰性であっても安心せず、大腸疾患リスクが高まる40代以上になったら、大腸カメラ検査を受けることをお勧めしております。
監修
 おきた内科クリニック
おきた内科クリニック
院長 沖田 英明
日本老年医学会 老年病専門医・日本内科学会 認定内科医・日本消化器内視鏡学会専門医・日本リウマチ財団 リウマチ登録医・日本糖尿病協会 療養指導医・認知症サポート医・広島県医師会認定かかりつけ医・日本抗加齢医学会 学会員・日本喘息学会 学会員