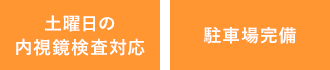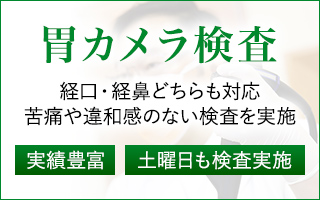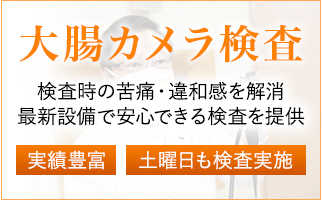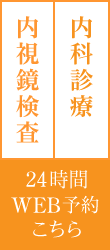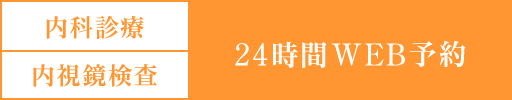診断書発行を依頼する際の基本的な流れとポイント
診断書は、病状や治療内容などを公的に証明するための重要な書類です。依頼から受け取りまでをスムーズに進めるために、以下の点を押さえておきましょう。
1. 依頼のタイミングと相手
いつ依頼するか?
診察時が最適です。 担当の医師に直接、診断書が必要な旨を伝えましょう。必要な記載事項などをその場で相談できるため、最もスムーズです。
診察後に必要になった場合は、まず病院の受付や窓口に相談してください。後日、改めて診察が必要になる場合もあります。
誰に依頼するか?
診断書を作成できるのは医師のみです。受付のスタッフはあくまで手続きの案内役となります。
2. 依頼時に伝えるべきこと・準備するもの
依頼をスムーズに進めるために、以下の情報を明確に伝えられるように準備しておきましょう。
提出先と目的:
「会社に休職届として提出する」「保険会社に請求するために必要」など、誰に、何のために提出するのかを具体的に伝えてください。目的によって記載すべき内容が変わる場合があります。
必要な記載事項:
提出先から指定されている項目(例:病名、初診日、治療期間、就労の可否、安静が必要な期間など)があれば、漏れなく伝えましょう。
指定の書式(フォーマット)の有無:
提出先から特定の書式の診断書を求められている場合は、必ずその用紙を持参してください。 特に指定がない場合は、医療機関が用意した一般的な書式で作成されます。
いつまでに必要か:
診断書の作成には時間がかかります。提出期限を伝え、余裕をもって依頼しましょう。
本人確認書類:
原則として本人からの依頼となります。健康保険証や運転免許証などの身分証明書が必要になる場合があります。
3. 発行にかかる期間
即日発行は難しい場合が多いと認識しておきましょう。
一般的な目安として、数日から2週間程度かかることが多いです。大規模な病院や、複雑な内容の場合はさらに時間がかかることもあります。
医師は通常の診察業務の合間に書類作成を行うため、時間がかかることを理解し、提出期限から逆算して早めに依頼することが大切です。
4. 費用
診断書の発行は、健康保険が適用されない「自費診療」です。
費用は医療機関や診断書の内容によって異なりますが、一般的な相場は2,000円~5,000円程度です。生命保険の請求などで特殊な内容が必要な場合は、10,000円程度になることもあります。
依頼する際に、費用がいくらかかるかを受付で確認しておくと安心です。
5. 記載内容に関する注意点
診断書には、医師が診察に基づいて判断した客観的な医学的事実が記載されます。
「少し長めに休めるように書いてほしい」といった、患者の希望をそのまま反映させることはできません。 虚偽の診断書を作成することは法律で禁じられています。
記載内容は、あくまで医師の専門的な判断に委ねられることを理解しておきましょう。
6. 受け取り方法
作成が完了したら、後日、医療機関の窓口で受け取るのが一般的です。
受け取りの際には、マイナンバーカード、本人確認書類、発行費用などが必要になります。
代理人が受け取る場合は、委任状や代理人の身分証明書を求められることがほとんどです。事前に必要なものを医療機関に確認してください。
医療機関によっては、郵送に対応してくれる場合もあります。
まとめ:スムーズに依頼するためのチェックリスト
✅ 事前準備
□ 提出先と目的を確認したか?
□ 必要な記載項目をメモしたか?
□ 指定の書式(用紙)はあるか?
✅ 依頼時
□ 診察時に医師に直接依頼する。
□ 上記の事前準備の内容を正確に伝える。
□ 発行にかかる日数と費用を確認する。
✅ 受け取り
□ 受け取りに必要なもの(診察券、本人確認書類、費用など)を確認・準備する。
これらの点を押さえておけば、医療機関とのやり取りがスムーズに進み、必要な診断書を円滑に受け取ることができるでしょう。